「せっかく通わせているのに、塾に行きたがらない…」
そんなお悩みを抱えるご家庭は、決して少なくありません。
塾は成績を伸ばすための手段として、多くの保護者にとって有力な選択肢。しかし、肝心の子どもが「行きたくない」と感じてしまっては、本来の学びの効果も期待できません。
この記事では、子どもが塾を嫌がる背景と、家庭でできる対応について詳しく解説していきます。
子どもが塾に行きたがらない主な理由
子どもが塾を嫌がるのには、いくつかの共通パターンがあります。まずは代表的な5つの理由を紹介します。
① 勉強そのものが「苦手・嫌い」だから
勉強への苦手意識が強いと、塾に行くこと自体が“プレッシャー”になります。
特に「わからないのに質問できない」、「ついていけない」などの体験があると、「行っても意味がない」と感じてしまいがちです。
塾は、「必ず行かないといけない」という場所ではないです。そのため、子どもたちからすると、学校や部活動が終わってから「わざわざ」行っているという感覚になりがちです。
わざわざ行っているのに、そこでさらにマイナスの体験が重なると、モチベーションはなかなか上がりません。
勉強が「楽しい」、「好きである」と思えているかどうかは大きな要素です。
② 塾の雰囲気や人間関係にストレスがある
先生との相性が合わない、周囲の生徒との関係がうまくいかない——。
塾は学習の場であると同時に、人間関係の場でもあります。
学校とは異なる環境に馴染めず、心理的に疲れてしまう子も少なくありません。
人間関係の悩みは打ち明けづらいという子どもも多いです。
もちろん、塾の先生に直接、「私はあなたと相性が悪いです」とは言い出せません。
かと言って、親に対しても、子どもたちなりに「高い学費を払ってもらっている」という感覚はあるため、自分の人間関係で心配をかけたくないという思いがある子もいます。
なかなか言い出せずに、ある程度時間が経ってから「実は…」となるケースが多いため、過剰に敏感になる必要はないですが、大人がある程度アンテナを張ってあげた方が良いです。
友達が多い環境の方が安心できるという生徒もいれば、集中したいから知り合いはいない方が良いという生徒もいます。どちらを望んでいるのかも確認しておくようにしましょう。
③ 塾=「勉強から逃げられない」というイメージがある
「勉強しなさい」「テストでいい点をとりなさい」とプレッシャーを受けてきた子どもにとって、塾は“自由を奪う場”のように映ることもあります。
塾での宿題チェックや、テストの点数、志望校の判定などは、子どもたちにとって、自信を得るきっかけになります。しかし、その反面、「自分はできていない」と突きつけるにも充分な材料であると言えるでしょう。
自分でも分かっているうえに、先生からも親からも指摘され、逃げ場がなくなってしまう。
どうして良いかわからず、ついに本人の感情が爆発してしまう。
クラス分けのテストの後や、受験前で発生することが多いパターンです。
それなりの危機感は必要ですが、性格によっては必要以上のプレッシャーになってしまっているかもしれません。
④ 疲れやストレスがたまっている
学校の授業や部活動で既に疲れているのに、さらに塾に行くことは身体的・精神的な負担になります。体力的な面だけでいうと、学校に行くことよりも大変でしょう。
学校行事や部活動が忙しい時期は、疲れた表情で塾に来る子も多いです。
そのような子が一生懸命授業を受けているのは非常にありがたいことでした。
しかし、なかには、「頑張りたい」という気持ちはあってもどうしても体力がついてこないという時期がある子もいるでしょう。
特に小学生や中学生のうちは、自分の疲労や感情をうまく言葉にできません。
「疲れているから休みたい」と言っても、親に「そんな理由で休むな」と言われてしまうかもしれない。そう考え、ただ「塾に行きたくない」、「やめたい」とだけ伝える子も多いです。
「疲れている」=「サボりたい」ではないケースもあります。睡眠時間等にも無理がないか確認をしましょう。
⑤本人にとって気がかりなことがある
- 宿題が終わっていないから怒られるかもしれない
- 遅刻していくのが恥ずかしい
- 小テストの勉強ができておらず自信がない
- 一度休んだことで気まずさを感じる
- プライベートで悩み事がある
思春期の子どもたちにとって、些細なことが優先順位の上位にくることは良くあります。
本人たちにとっては、これらが塾に行けないほどの大きな理由なのです。一回限りで解決することもありますが、長く続くようなら、塾に相談しましょう。
保護者にできる“5つの対応策”
「行きたくない」と言われたとき、どう接すれば良いのでしょうか。
ここでは、無理に押しつけるのではなく、子どもと信頼関係を築きながら対応するためのポイントをご紹介します。
① 否定せずに「まず気持ちを聞く」
「どうして行きたくないの?」「何がしんどいの?」と、子どもの言葉を引き出す姿勢が大切です。
このとき、すぐにアドバイスをせず、ただうなずくだけでも構いません。子どもにとっては「わかってもらえた」と感じられるだけで安心します。
子ども自身も、休むことに対する罪悪感や将来への不安を感じていることが多いです。子どもにとって言語化しにくい場合もあるでしょうが、粘り強く本心を話してくれるのを待ちましょう。
② 選択肢を提示する
「行くか、行かないか」だけでなく、塾の種類を変える・コースや曜日を見直す・別の教材を検討するなど、選択肢を用意することが大切です。
「今の塾に通い続けること」だけが正解ではありません。家庭学習やオンライン学習など、学びの環境は様々あります。
ただし、根本的な原因が解決しないと、環境を変えても同じことが繰り返される可能性があります。「負担を減らせば何とかなる」とは限りませんので、焦りすぎずに、子どもに合ったスタイルを一緒に探っていくことが重要です。
③ 学びの目的を一緒に考える
「なぜ勉強するのか」「将来何をしてみたいか」といった会話を通して、学びの動機づけを行いましょう。目標があると、子ども自身が「必要だから行く」と考えられるようになり、自発性が育まれます。
塾の講師に相談をしてみるのも良いと思います。今までの生徒の具体的な話を聞くことで、子ども自身も身近な例としてイメージしやすく、「自分もそうなりたい」と、学習の目的を見つけるヒントになることもあります。
④ 成績以外の成長を認める
「ちゃんと行けたね」「前よりノートが丁寧だね」など、結果ではなくプロセスを褒めることも有効です。
親だからこそ気づける本人の変化があるはずです。
自分の成長に気づくことで、「頑張ればできる」と子どもが思えるようになり、学習に対する前向きな気持ちが生まれます。
⑤ 一時的に“離れる”ことも選択肢
無理に継続させることで、勉強嫌いが加速する場合もあります。どうしても本人が拒否する場合は、いったん塾を休む・別の方法を検討することも視野に入れましょう。
大切なのは、塾に通い続けることではなく、「学びを継続すること」です。塾はあくまで手段のひとつです。
子どもにとっての“安心基地”であること
子どもは、まだ自分の感情や不安をうまく言葉にできません。大人の視点からすると「甘えている」と感じるような言動も、実は小さなSOSであることが多いのです。
まずは「親が味方だよ」という姿勢を持ち、子どもの本音に寄り添うことが、結果として最も効果的な学習サポートにつながります。
塾に行くことが目的ではなく、子ども自身が成長を感じられることを目的に、親子で学びの形を模索していきましょう。
🐧塾に行かない=失敗ではない
塾に行かない選択は、決して後ろ向きなものではありません。
大切なのは、その理由を正しく受け止め、子どもに合った学び方を一緒に探すこと。
悩みながらも子どもの成長を願う親の姿勢こそが、最大の教育力です。
これからも、お子様の学びに寄り添いながら、家庭でできるサポートを一緒に考えていきましょう。
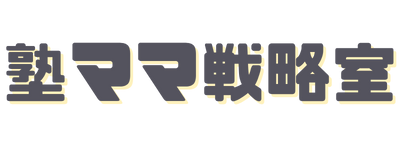
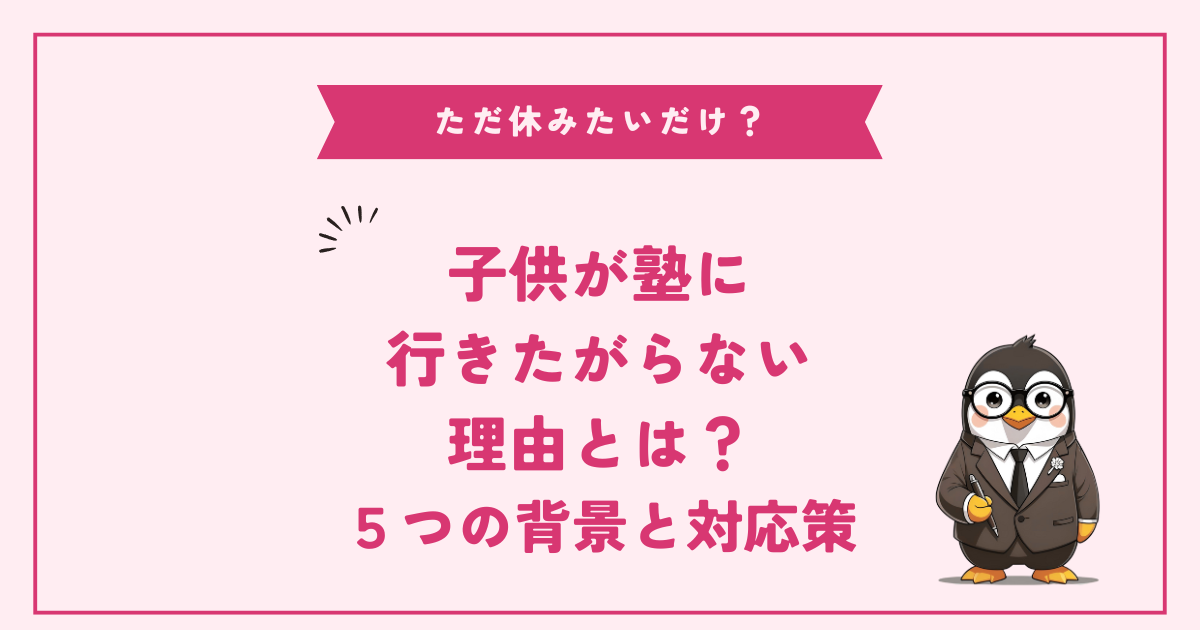
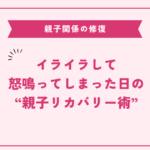
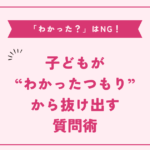
コメント