「スマホやゲームばかりで、全然勉強に集中してくれないんです」
面談や保護者会で、必ずと言っていいほど出てくるこの悩み。
しかし、実はこれ、多くの家庭が抱えている“今どき”の課題です。
スマホもゲームも、今や生活に根付いた存在。
大人ですら、ついつい時間を忘れて使ってしまうもの。
だからこそ、子どもたちに「適切な距離感」と「上手な使い方」を教えることが、
私たち大人の大切な役割なのです。
スマホ・ゲームに熱中する子どもの“本音”とは?
一見、「ただの遊び」に見えるスマホやゲーム。
でも実は、子どもたちにとっては以下のような役割を果たしているのです。
- 頑張った後のごほうびとしての「癒し」
- 現実から少し離れられる「逃げ場」
- 自分のペースでできる「安心感」
- 友達とのつながりを感じられる「共通の話題」
つまり、スマホやゲームに夢中になるのは、「ただの怠け」ではなく、
そこに心理的な満足があるからなのです。
なぜスマホ・ゲームばかりになってしまうのか?
① 目標が曖昧で、勉強に意味を見出せていない
「何のために勉強するの?」という問いに、はっきり答えられる子は実は少数です。また、子どもたちは「勉強をしなければならない」、「早く目標を決めなくてはならない」という見えないプレッシャーを感じています。勉強に対してマイナスイメージを持って取り組んでいる場合、そのような現実から離れるための「逃げ場」としての利用も多いです。
スマホやゲームは、すぐに成果や達成感を得られるため、意味を感じにくい勉強よりも楽しく感じてしまうのは当然の流れです。
② 自己肯定感が低く、「どうせやっても無理」と感じている
過去の失敗や注意の積み重ねにより、「やってもどうせうまくいかない」と思い込み、勉強から遠ざかってしまうこともあります。スマホのゲームは時間をかければわかりやすく強くなるものが多いため、勉強で満たせないモチベーションや承認欲求を、ゲームを通して獲得しようとする子どもも多いです。
③ 時間の管理が苦手で、ダラダラと続けてしまう
スマホやゲームは終わりが見えづらく、時間を忘れて続けてしまいがちです。
ゲームはプロの作り手が離脱者を出さないように作っていますし、動画も最後まで見てもらえるように、配信者によって様々な工夫が凝らされています。
学習のリズムが崩れている場合、時間の管理ができないことで、生活全体がスマホ中心になることもあります。
「やめさせる」よりも「付き合い方を教える」
完全に禁止するという方法もありますが、
多くの場合、親子の関係がギクシャクしたり、隠れてやるようになってしまったりと、
根本的な解決にはつながりません。
大切なのは、スマホやゲームを“管理する力”を育てることです。
家庭でできる!スマホ・ゲームとのバランスの取り方5選
① 「勉強→ごほうび」で自然な流れを作る
「宿題が終わったら30分ゲームOK」といったルールを決めましょう。
ポイントは、“何をどこまで終えたら使えるか”を明確にすることです。
一貫性を持って運用することで、子どもも納得して動けます。
② タイマーやスケジュールを活用して見える化
アナログのタイマーでも、スマホのアプリでもOK。
「あと10分だけ!」を防ぐために、
視覚的に時間の区切りを伝えましょう。
③ “選ばせる”ことで主体性を育てる
「勉強する?しない?」ではなく、
「先に宿題?後で?」「今夜はゲーム30分or動画20分、どっち?」など、
子どもに選択の余地を持たせましょう。
「自分で決めた」という意識が、責任感を育てます。
④ スマホを「学びの道具」として活用する
学習アプリやタイピングゲーム、調べ学習など、
スマホやタブレットも使い方次第で立派な学びのツールになります。
「遊びと学びの境界」を一緒に探していく視点が大切です。
⑤ 親も一緒に「デジタルとの距離」を見直す
「親はずっとスマホを見てるのに…」という不満を、子どもは実は感じ取っています。
スマホを使う姿を“見せる・見られる”こと自体が、学びの一環になるのです。
◆ 親子で話し合いたい“スマホルール”の作り方
- 平日の使用時間・タイミングを決める(例:勉強後30分)
- リビングのみで使うなど、使用場所の制限
- アプリやコンテンツは一緒に選ぶ
- 週1回、ルールの振り返りタイムを設ける
親が一方的に決めるのではなく、子どもと話し合って決めることで、
ルールが「押し付け」ではなく「約束」になります。
🐧スマホとの付き合い方は“未来を生きる力”
これからの社会では、スマホやデジタルとの付き合い方がますます問われます。
大切なのは、「与えないこと」ではなく「使い方を教えること」。
家庭でのちょっとした工夫と声かけが、
子どもの“学びへのスイッチ”を押すきっかけになります。
「どうせダメだ」と決めつける前に、
どんな風に“味方”になれるかを一緒に考えてみましょう。
スマホもゲームも、正しく使えば勉強の応援団になってくれますよ!
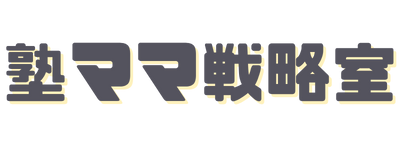
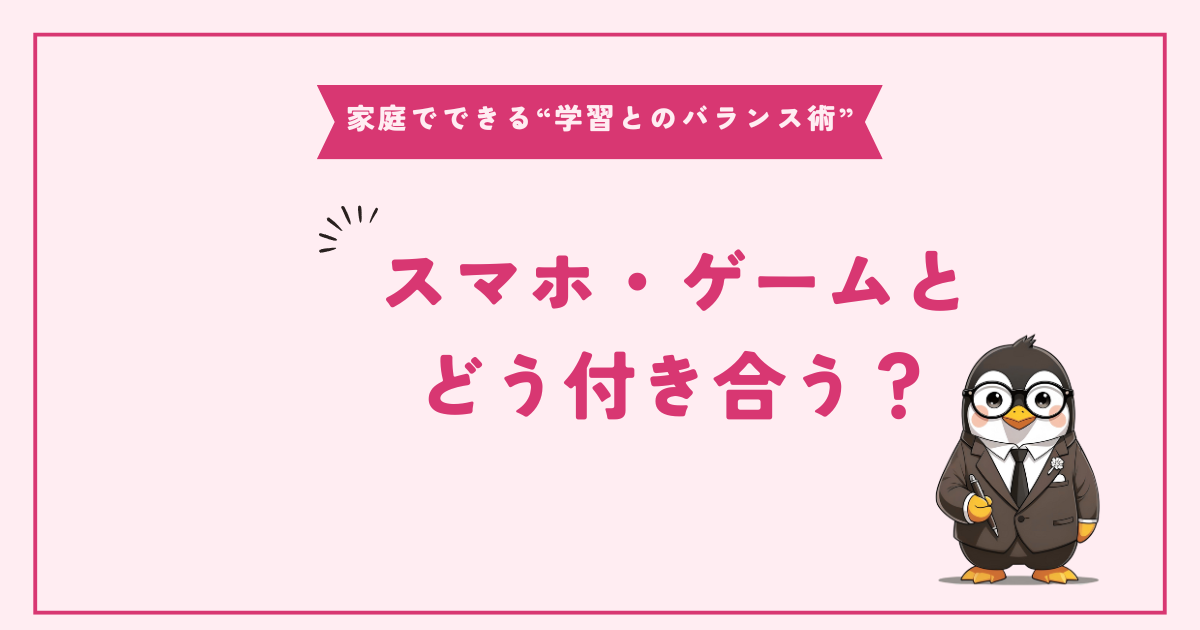
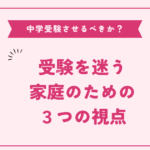
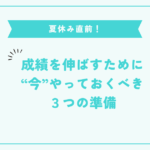
コメント